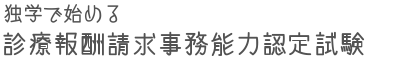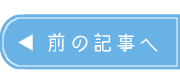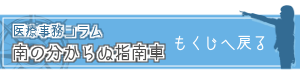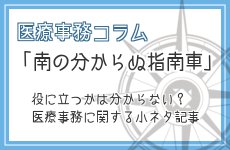学科試験と実技試験、こんな時間配分で解いてみた
 診療報酬請求事務能力認定試験の試験時間は3時間と長い。試験の時間帯は午後1時から4時までで、お腹もふくれた昼下がりです。勉強を始める前は、検定試験に3時間も必要なのか…?と思ったりしたわけですが、いざ勉強を始めてみるとそうも言っていられなくなる。
診療報酬請求事務能力認定試験の試験時間は3時間と長い。試験の時間帯は午後1時から4時までで、お腹もふくれた昼下がりです。勉強を始める前は、検定試験に3時間も必要なのか…?と思ったりしたわけですが、いざ勉強を始めてみるとそうも言っていられなくなる。
実際に勉強を始めた方は、もう実感していると思いますが、学科にしても実技にしても、とにかく時間がかかります。
例えば学科試験の場合、○×問題のたった1題に、15分20分とかかったりします。点数表はとにかく厚くて文字が小さい。そしてページは薄い。辞書的なものなので、仕方ないといえばそれまでなんだけれど、とにかく慣れるまでは点数表の扱いに疲弊します。
まず、似たような単語が多く、索引からキーワードを見つけるのに一苦労。とくにサ行なんてじっくり探していくから、かなりの時間がかかります。それで欲しい情報がすぐに見つけられればいいけれど、最初のうちはそうそう簡単にはいきません。
こちらにすでに目を通してくださった方はお分かりだと思いますが、学科試験で問われる内容は、かなりこまかいところに書いてあることがほとんどです。だから、なんとなくこのあたりにありそうだな、ということが分かるようになるまでは、索引から開いたページの隅々まで必死に読んで探してしまいます。
学科試験は全部で20問です。その中に○×問題が各4題ありますので、全部で80題の○×問題を解くことになります。正答率が上がってきたら、そのうちの6〜7割を解くだけで正しい選択肢を選ぶことができるようになりますが、それでも単純計算で1題1〜2分で解かないと間に合わないことになります。
その一方で実技試験はというと、こちらも同様にものすごく時間がかかります。日常的に手で文字を書く機会が減っているので、小さめの字で医療用語ばかりを書き続けるのは、なかなか大変な作業です。それでも、カルテの内容を読み取れなかったり、間違った項目を算定していたりと、何時間もかけて作成したレセプトも解答を見ると間違いだらけです。
そこで試験を侮っていた自分に気づきます。…3時間って、短い…。昼下がりだからって、うとうとしている余裕はない…。
 そこからは時短を目指して答練を繰り返したわけですが、その時短にも限界があります。点数表を開くのも、文字を書くのも、ある一定の速さより早くはできません。では、次にどうするかと考えましたが、あとは時間配分で調整するしかありませんでした。
そこからは時短を目指して答練を繰り返したわけですが、その時短にも限界があります。点数表を開くのも、文字を書くのも、ある一定の速さより早くはできません。では、次にどうするかと考えましたが、あとは時間配分で調整するしかありませんでした。
この試験は、合格ラインは7割程度で合格できる試験です。絶対とは言い切れませんが、合格者の割合をみるとだいたい30%前後に集中しているので、おそらく回によって多少の調整はされているでしょう。とすれば、難しい問題が出題されたとしても、受験者みんなができなければある程度の合格は見込めるわけです。それなら、時間内に全部できて、全部正解する必要はないわけです。
試験時間は3時間。これだけは絶対に変わりません。この時間内に、学科も実技も合格ラインの7割に達するために、私は学科、外来レセプト、入院レセプトに時間を振り当てました。
外来レセプト30分、入院レセプト1時間15分、学科試験を1時間15分として、もしその制限時間を超えた場合は、全部できていなくても次に移りました。
学科と実技、どちらか苦手がときかれれば学科と答えます。レセプトは、繰り返し作成していくと、最初のうちは何時間もかかっていたものも、どんどんと短縮されていきます。そしてそれが問題によって長くなったりすることはあまりありません。しかし、学科は私の場合はそうはいきませんでした。たった1題の○×問題でも、資料からうまく答えを探し出せなければ、時間はいくらでもかかってしまいます。勉強の段階で学科を1時間以内に終わらせることができたとしても、本試験でもその時間でできるということにはならない気がしていました。
そんなわけで、制限時間内に完成させられる可能性の高い、外来レセプト、入院レセプトを先にやり、あまった時間すべてを学科に充てました。苦手な学科を、時間に追われずにとりかかれたのが、合格できたひとつの要因だったのかもしれないと思っています。
もし、時間配分をどうしようか悩んでいる方で、学科が苦手という方はこの方法で一度やってみてください。