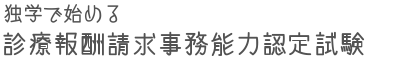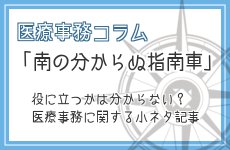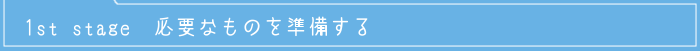
 医療事務の資格試験と聞くと、レセプト作成をイメージする方も多いでしょう。診療報酬請求事務能力認定試験においても、実技試験はもちろんレセプトの作成です。
医療事務の資格試験と聞くと、レセプト作成をイメージする方も多いでしょう。診療報酬請求事務能力認定試験においても、実技試験はもちろんレセプトの作成です。
昨今では電子カルテ化が進み、健康保険への診療報酬請求もオンラインになったため、実務で手書きのレセプトを作成することはまずありません。ではなぜ、一見無駄のようなものを試験の内容にするのか、という疑問が沸いてくるでしょう。
それは、『手書きでレセプトを作成できる』ということが、『医療事務の知識をしっかり身に着けている』と確実に判断できるからです。手書きでレセプトを作成する場合、さまざまなことに注意が必要になります。病名に対して算定可能な管理料などはないか、同時算定不可能なものが同時算定されていないか、包括点数のものを単独点数で計算していないかなど、作成する上でのチェック項目がたくさんあります。手書きでレセプトを作成できるということは、そのチェック項目が頭に入っているということです。また、行なった診療行為に対して算定方法が不確かな場合に、それを調べる方法が身についているということにもなります。
実技試験で必要なものは主に点数表と完全攻略マニュアル、電卓です。どんなものが分からない方はおすすめ教材をご覧ください。
 教材をそろえる
教材をそろえる
| おすすめ実技試験対策アイテム |
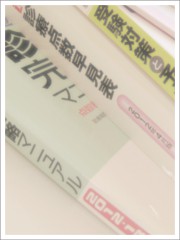 ■問題集 (医学通信社) ■問題集 (医学通信社)
■診療報酬・完全マスタードリル ■点数表(医学通信社) ■診療報酬完全攻略マニュアル ■問題集別冊付録の点数表 ■電卓 ■ストップウォッチ ■シャープペンシル ■赤いボールペン(先の細いものがおすすめ) ■付箋 ■外来用レセプト ■入院用レセプト ■実技用備忘記録 |
これらの教材は、私が試験勉強をするときに主に使っていたものです。人によっては必要のないもの、逆にここにはない必要なものがあるかもしれません。ここで紹介する勉強法を参考にしながら、自分の勉強法を確立させていってください。
 番号と診療項目を覚える
番号と診療項目を覚える
 これは、作業的な準備ではなく、頭の準備です。レセプト作成は基本的に暗記をするは必要ありませんが、これだけは覚えてからレセプト作成に臨んでください。
これは、作業的な準備ではなく、頭の準備です。レセプト作成は基本的に暗記をするは必要ありませんが、これだけは覚えてからレセプト作成に臨んでください。
診療項目は、11番から97番までの番号に振り分けられています。レセプト摘要欄はその番号順に書かれています。カルテの情報から、どれが何番の診療項目かを読み取り、番号の小さいものから書いていかなければなりません。
まずはレセプトを手元に置いて下さい。問題集にもついていますし、点数表やマニュアルにもついています。こちらで見ていただいてもかまいません。その左側の病床名の下に、番号とその項目が書かれています。これらをすべて覚えてください。
持ち込みOKなら、暗記する必要はないのでは?と思われるかもしれませんが、これが頭に中に入っていないと、レセプトの作成に手間取ります。制限時間内に作成するためには、これだけは必ず覚えてください。
| 暗記する番号と診療項目 |
| ●11番 初診 ●12番 再診 ●13番 医学管理 ●14番 在宅 ●20番 投薬 ●21番 内服 ●22番 屯服 ●23番 外用 ●24番 調剤 ●25番 処方 ●26番 麻毒 ●27番 調基 ●30番 注射 ●31番 皮下筋肉内 ●32番 静脈内 ●33番 その他 ●40番 処置 ●50番 手術麻酔 ●60番 検査病理 ●70番 画像診断 ●80番 その他 ●90番 入院 ●91番 入院基本・加算 ●92番 特定入院 ●97番 食事・生活 |
| 暗記する番号と診療項目【暗記用】 |
| ●11番 初診 ●12番 再診 ●13番 医学管理 ●14番 在宅 ●20番 投薬 ●21番 内服 ●22番 屯服 ●23番 外用 ●24番 調剤 ●25番 処方 ●26番 麻毒 ●27番 調基 ●30番 注射 ●31番 皮下筋肉内 ●32番 静脈内 ●33番 その他 ●40番 処置 ●50番 手術麻酔 ●60番 検査病理 ●70番 画像診断 ●80番 その他 ●90番 入院 ●91番 入院基本・加算 ●92番 特定入院 ●97番 食事・生活 |
これですべてです。実質的にはそれほど多くはありません。暗記用の番号と診療項目は、オンマウスで表示されるようになります。暗記の確認にお役立てください。