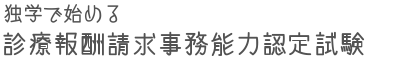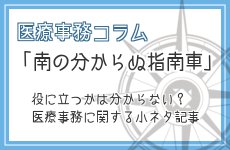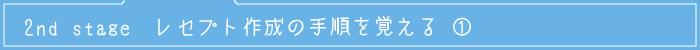
 それではここから、レセプトの作成に移ります。レセプトの作成は、勉強というよりも作業と言ったほうが適切かもしれません。レセプト作成にあたり必要な項目を、あえて暗記をする必要はありません。ただ、繰り返し何度もレセプトを作成していると、自然とよく使う項目は暗記してしまいます。見方を買えれば、勝手に覚えてしまうほど繰り返せば合格レベルに達していると考えることもできます。
それではここから、レセプトの作成に移ります。レセプトの作成は、勉強というよりも作業と言ったほうが適切かもしれません。レセプト作成にあたり必要な項目を、あえて暗記をする必要はありません。ただ、繰り返し何度もレセプトを作成していると、自然とよく使う項目は暗記してしまいます。見方を買えれば、勝手に覚えてしまうほど繰り返せば合格レベルに達していると考えることもできます。
まずは、基本的なレセプトの書き方を覚えてください。一連の流れを覚え、その順番で確実に記入をしていけば、記入漏れによる間違いを減らすことができます。
基本的に問題集は、本試験を意識して作られているため、初学者にはハードルが高い問題ばかりが載っています。医療事務の勉強が初めての方は、完全・マスタードリル
![]() から始めたほうがいいでしょう。
から始めたほうがいいでしょう。
 ①患者情報を書き写す
①患者情報を書き写す
カルテの上の方を見てください。保険請求に必要な個人情報が記載されています。その情報をすべてレセプトに書き写してください。患者名、生年月日、性別あたりはそれほど問題ないでしょう。一文字一文字間違えないように記入してください。保険情報に関しては少し注意が必要です。以下の表を参考にしてください。
| 保険証の区分 | 本人の場合……被保険者氏名と患者名が同一 家族の場合……被保険者氏名と患者名が異なる |
|---|---|
| 保険の種類 | 社保・国保……保険者番号が8桁または6桁の一般の方およびその家族 公 費 ……保険に加入しておらず、公費負担番号のある方 後期高齢 ……75歳以上の方 退 職 ……一定期間以上労働し、年金を受け取っている方で75歳未満の方 |
また、これ以外にも、6歳未満の小児の場合は『六外』『六入』に○を付ける、後期高齢者で自己負担割合が3割の方は『0高外7』『0高入7』に○をつけてください。保険者番号および記号・番号についても正確に記入してください。
 ②病院の情報や届出情報を確認する
②病院の情報や届出情報を確認する
 実技問題の一番最初に書かれている項目です。病院の情報について記載されており、この情報をもとにして算定可能な管理料等があれば必ず算定するようにしてください。
実技問題の一番最初に書かれている項目です。病院の情報について記載されており、この情報をもとにして算定可能な管理料等があれば必ず算定するようにしてください。
病床は何床なのか、何科を標榜しているのか、薬剤師は常勤しているか、どんな届出がされているかを確認しましょう。診療時間、休日についても同様です。診察時間外の急患の場合は時間帯に応じた時間外加算があります。カルテに書かれている受診時間に注意して、算定ミスをしないよう心掛けてください。
問題に慣れるまでは、直接的に関連性を見つけられない項目を見落としがちですが、試験によく出題されるものはそれほど多くありません。繰り返し解いていくうちに次第に身についてくるものですので、初めのうちは見落としても気にせずに学習を進めていってください。
 ③病名を書き写し、初診か再診かを確認する
③病名を書き写し、初診か再診かを確認する
氏名等と同様に、カルテに記載されている病名をレセプトの『傷病名』のところに、間違いなく記入します。左右上下の部位がある場合は特に気を付けてください。傷病名には必ず主傷病名があります。カルテに(主)と書いてある病名です。これを傷病名のいちばん上に書いてください。主傷病名以外のものがいちばん上に書いてあると、問題として正解にはなりません。また、診療開始日にも注意が必要です。診察していない日や、生年月日より前の日付にならないよう、しっかりとカルテを見てください。
次に、診療開始日から、初診か再診かを読み取ってください。診療明細書の診療月より前に診療を開始している病名があり、それが継続している場合は、診療月に新たな傷病名が追加されても再診料を算定します。診療月以前から継続している病名が、診療月に治癒し、その後他の傷病等で再度診療行為を行なった場合、2回目の受診は初診料を算定します。診察日時点で継続している傷病がない場合、その日の診療は初診と考えてください。
そのあとに、診療実日数を数えてください。問題によっては、1日に2回以上受診することもありますが、回数ではなく日数であることに注意してください。