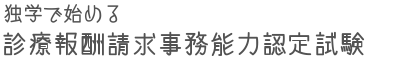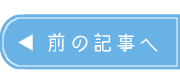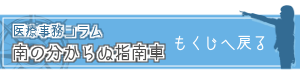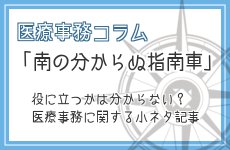受かるには、こんな力をつければよい。
 言うのは簡単、やるのは難しい。でもあえて、あえて言ってみる。この試験は『慣れ』で受かる試験です。だから、試験勉強が『勉強』よりも『作業』だと感じるようになれば、もうこっちのものです。
言うのは簡単、やるのは難しい。でもあえて、あえて言ってみる。この試験は『慣れ』で受かる試験です。だから、試験勉強が『勉強』よりも『作業』だと感じるようになれば、もうこっちのものです。
医療事務の仕事は、基本的には毎日同じことの繰り返しです。病院を訪れた患者さんといちばんに顔を合わせて、カルテをまわして、診察が終わったら診療項目を入力、会計処理、事務的な説明や案内をして、いちばん最後に患者さんを見送ります。
毎日いろいろな方が、いろいろな症状で病院に訪れるので、全く同じ日は1日もありません。それでも、基本的な流れは同じで、その場に応じて臨機応変に応対をします。
この一連の流れを行なうには、ある程度の知識が必要ですが、丸暗記の勉強でどうにかなるものではありません。どんな仕事にも共通することかもしれませんが、医療事務は、その場その場に順応して行なう作業です。初めのうちはあれこれ考えてしまって、あたふたしてしまいますが、だんだんと慣れていくうちに反射的にからだが動くようになります。
この試験は、その仕事と同じものだと考えてください。初めのうちは知識を頭に入れるための『勉強』です。しかしそのあとはスピードを重視した『作業』です。
初めは、レセプトの書き方や、算定のルールなどを覚えていきますが、診療項目をすべて暗記するのは到底不可能です。ある一定の知識を得たら、あとは分からないことがあるたびに点数表で調べるようにすれば、レセプトを作成していけます。不確実な記憶をするより、調べるスピードを速める能力を身に着ける方が重要です。
 どんな資格にも、合格に必要な条件があります。例えば、専門的な知識をもって、一般の人に分かりやすく説明する能力が必要な弁護士や社労士などは、その資格に合格するためには多大な量の暗記を必要とします。一方で、医療事務員はというと、仕事をする上では点数表を見ることが前提とされているので、暗記する項目はほとんどなく、点数表を使いこなせる能力を必要とします。
どんな資格にも、合格に必要な条件があります。例えば、専門的な知識をもって、一般の人に分かりやすく説明する能力が必要な弁護士や社労士などは、その資格に合格するためには多大な量の暗記を必要とします。一方で、医療事務員はというと、仕事をする上では点数表を見ることが前提とされているので、暗記する項目はほとんどなく、点数表を使いこなせる能力を必要とします。
この資格は、合格ラインが7割の資格です。医療事務の中では最も難しいと言われていて、合格率も30%前後と他の医療事務資格と比べるととても低いです。
しかし、決して難解な試験というわけではありません。何をやっているのかさっぱりわからない、数学や物理の試験とは違います。呪文を唱えるようにして単語を覚えた、英語や古典のテストとも違います。どちらかというと部活のようなもので、いったん基本的なルールを覚えたら、あとはひたすら練習を積むことでどんどん上達していく、そんな感覚に近いものです。
この試験の合格率がそれほど高くないのは、資格の勉強が『勉強』の段階であって『作業』の粋まで達していない受験者が多いからだと思います(あくまで勝手な予想です)。この試験に合格するには、何度も問題を繰り返しといて、『勉強』を『作業』にしてしまえばいいのです。
最初にも言ったとおり、言うのは簡単。頭で理解するのも簡単です。でも実際にやるのはやっぱり大変です。点数表は重いので、私はこの試験の勉強中は、肩こりがひどくなりました。肩を通り越して背中まで痛くなりました。頭はそんなに使わないけれど、肉体的に大変な試験だなと心底思います。
もしも、勉強が途中で辛くなったときは、ちょっと休んで一息ついて、そのあとに少しこの勉強の見方を変えてみてください。仕事に就いてから受けるはずだった肩こりや腕の痛みや精神的な苦痛を、先に受けている。だから、仕事に就いてからきっと少し楽になる。そう思いながら、『勉強』から『作業』の極みへと駆け上がっていってください。