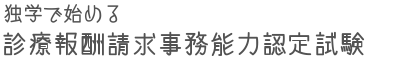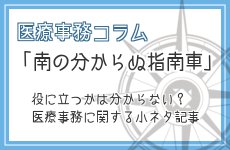準備ができたらいよいよ勉強のスタートです。初志貫徹、今の気持ちを忘れないようにしてください。
準備ができたらいよいよ勉強のスタートです。初志貫徹、今の気持ちを忘れないようにしてください。
勉強期間は2ヶ月~6ヶ月が目安です。とりあえず受験料を払ったけれど、1ヶ月前くらいから始めればいいかな?という考えは厳禁です。よほど試験慣れしていて、処理能力の高い方は別ですが、そうでなければ合格レベルに達するまでに2ヶ月はかかります。
週末しか時間の取れない方や、ゆとりをもって勉強を進めたい方は6ヶ月、1日平均4~5時間の勉強時間を確保できる方は2ヶ月と考えて自分の学習計画を立ててください。
 試験の形式を知る
試験の形式を知る
まずは学科試験がどういう形式で出題されるのかを知りましょう。学科試験は五者択一の選択問題です。過去問を見ても変更なくこの形式で出題されているので、次回以降もこの形式に変更はないでしょう。
|
問○ 次の文章のうち正しいものはどれですか。 (1) 同一日に3つの診療科を受診する場合、1つ目の診療科を再診で、2つ目及び3つ目の診療科を a.(1)(2) b.(2)(3) c.(1)(3)(4) d.(1)~(4)のすべて e.(4)のみ |
この問題は私が簡単に作ったものです。本試験の問題は、もう少し難易度が高くなっていますが、形式はこの通りです。4題の○×問題があり、その○×の組み合わせと合うものを下の『a』~『e』の中から選びます。
学科問題は全部で20問ですが、各問題につき○×問題が4題ありますので、実質的には○×問題を80題解くことになります。
 1題ずつていねいに解く
1題ずつていねいに解く
この試験はスピードが要求される試験であると、たびたび言っていますが、初期段階では時間はあまり意識せず、1題1題ていねいに解いていくことを目指してください。基礎をしっかりと固めておけば、後半戦で穴を見つけてしまったり点数が不安定になったりしません。
では、上の例題を使って解き方を説明していきます。正しいものを探せばいいわけですから、それぞれの○×問題が正しければ○、間違っていれば×を付けて解いていきます。このときに、問題集に直接書き込んだりせずに、解答用紙に○×を書くようにしてください。この試験は、繰り返し問題を解くことで合格する試験です。書き込みをしてしまうと、1回通りしか解くことができなくなります。どうしても書き込みながら解きたい方は、コピーを取ってそちらと使うようにしてください。
 では例題の(1)に注目してください。この問題は『初・再診』の問題です。診療点数の関係のあるものは、まず点数表から探し出すことを基本としてください。実務経験のある方や、すでに他の医療事務資格をお持ちの方で、この問題が『同日初診料』のことを問う問題だと分かる方は、索引の『同一初診料』を探し、該当ページから正解を導き出してください。初心者の方は、文章中のキーワードになりそうな単語を拾い、索引から近似する単語を探し出してください。この問題の場合であれば、『同一日』『初診』に注目して索引を開くと、『同一日複数科受診時の初診料』ということばが見つかります。そこから該当ページで正解を導き出してください。
では例題の(1)に注目してください。この問題は『初・再診』の問題です。診療点数の関係のあるものは、まず点数表から探し出すことを基本としてください。実務経験のある方や、すでに他の医療事務資格をお持ちの方で、この問題が『同日初診料』のことを問う問題だと分かる方は、索引の『同一初診料』を探し、該当ページから正解を導き出してください。初心者の方は、文章中のキーワードになりそうな単語を拾い、索引から近似する単語を探し出してください。この問題の場合であれば、『同一日』『初診』に注目して索引を開くと、『同一日複数科受診時の初診料』ということばが見つかります。そこから該当ページで正解を導き出してください。
初期段階では、問題文の内容から、キーワードとなる単語を見つける力をつけることを心がけてください。初めのうちは、点数表などの扱いに慣れていないこともあり、数問解くのに1時間かかってしまうこともあります。しかし、焦って間違えてしまうよりも時間をかけて正解を導き出すことの方が大切です。1題ずつていねいに解いていってください。
 選択肢の組み合わせを覚えつつすべて解く
選択肢の組み合わせを覚えつつすべて解く
上の例題を見て気付いた方もいらっしゃるでしょう。問いで、『正しいものはどれですか』と聞かれていますが、○×問題4題に対し、選択肢はたったの5つです。選択肢はどの問題においてもすべてこのパターンです。本来なら16通りの組み合わせがあるわけですが、選択肢は5通りの組み合わせしかないため、○×問題のすべてを解かなくても正解を導き出すことができます。例えば、上の例題の場合、(1)の内容は正しくないので『×』です。(2)の内容は正しいことが書かれているので『○』です。この時点で、選べる選択肢は『b』しかありません。しかし、この段階で、(3)(4)を解かないということはしないようにしてください。
この段階では、出題傾向や難易度を肌で感じることや、キーワードを探す力を身に着けることが目的です。選択肢は、問題を解きながら徐々に暗記するようにしてください。そして、どの○×問題も飛ばすことなく解いていってください。
 間違えたところを直す
間違えたところを直す
 はじめのうちは、点数表の独特の文章に慣れず、読み間違いや見落としにより間違えてしまうことがよくあります。時間をかけて解いたものが間違っていると、落ち込んだりモチベーションが下がったりすることもありますが、この段階ではあまり気にせずに勉強を進めていってください。
はじめのうちは、点数表の独特の文章に慣れず、読み間違いや見落としにより間違えてしまうことがよくあります。時間をかけて解いたものが間違っていると、落ち込んだりモチベーションが下がったりすることもありますが、この段階ではあまり気にせずに勉強を進めていってください。
初学者が初めて解く問題で間違ってしまうのは仕方のないことです。それ自体は決して悪いことではありません。しかし、間違いを直さず放っておくのはよくありません。間違えた問題は、次に似たような問題が出題されたときに間違えずに答えられるように直しておく必要があります。読み間違えたところ、見落としたところは赤で線を引いておきましょう。解答に書いてある重要事項は、点数表等にも書き加えておくといいでしょう。
それを繰り返しているうちに、探すべき場所や答えのありそうな場所もだんだんと分かるようになります。