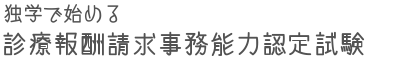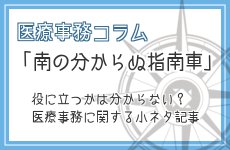基本的な知識が身についてきたら、次のステージへ進んでください。目安としては、問題集を1回通り解き終わったら、こちらのステージへステップアップしてください。
基本的な知識が身についてきたら、次のステージへ進んでください。目安としては、問題集を1回通り解き終わったら、こちらのステージへステップアップしてください。
独学の場合、確保できる勉強時間やペースが異なるので、一概にこうでなければ合格できないということはありませんが、試験前1〜2ヶ月前までにこちらのステージに進んでいることが理想です。
 試験の難易度と癖を知る
試験の難易度と癖を知る
一通り問題集をこなしてみて、この試験の難易度がなんとなく分かってきたのではないでしょうか?診療報酬請求事務能力認定試験は、医療事務資格の中では最難関と言われているだけあり、誰でも受かる試験ではありません。実際に、この試験の合格者は、初回受験者よりも再受験者の方が多いです。
そう聞くと、とても合格なんて無理だと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そこまで心配する必要はありません。やるべきことを最後まできちんとこなせば、ちゃんと合格できる試験です。試験を甘くみて適当に勉強をしたり、試験直前になってあれこれ詰め込んだりせず、コツコツと進めていけばたいていは合格できます。勉強の段階で合格点に達していれば、本試験ではほぼ合格となります。まずはそのことを念頭に置いて勉強を続けてください。
その上で、問題の癖を知りましょう。どんな資格試験にも、その試験特有の癖があります。では、診療報酬請求事務能力認定試験の場合はどうでしょうか?さまざまな意見があるとは思いますが、私が感じたこの試験の癖をいくつか挙げてみます。
|
■過去問をベースに作成されており、大きな変化はない。 |
【用語の説明】 |
|
|---|---|
| 保医発通知 | 厚生労働省保険局医療課長名で通知されているもので、水色の枠の外に小さく書かれていることがら |
| 通則 | 点数算定の原則と定めたもので、薄紫色の枠で囲われれいることがら |
| 告示 | 厚生労働大臣が定める基準等で、点数表の第2編にまとめられていることがら |
| 参考 | 公式の規定ではないが行政機関等に確認もので、青色文字で書かれたことがら |
| 事務連絡 | 厚生労働省から出された事務連絡であり、事務連絡マークのあとに濃紺文字で書かれたことがら |
| 改定事項 | 直近の点数改定により新規、変更されたものであり、緑色の文字、下線、囲い文字によることがら |
一通り問題集を解いているので、すでに気付いている方もいらっしゃるかもしれません。上記のことがらを今まで以上に意識しながら、この試験の癖をからだで覚えるようにしてください。
 自分の弱点を知る
自分の弱点を知る
 繰り返しいろいろな問題を解いていると、次第に自分の苦手な部分がはっきりとしてきます。自分の弱点が分かったら、それを克服しなければなりません。この試験は、勉強している時点で間違えやすかったところは、本試験でも間違える可能性がとても高い試験です。
繰り返しいろいろな問題を解いていると、次第に自分の苦手な部分がはっきりとしてきます。自分の弱点が分かったら、それを克服しなければなりません。この試験は、勉強している時点で間違えやすかったところは、本試験でも間違える可能性がとても高い試験です。
では、どのような対策をしたら克服できるのかを考えてみてください。例えば私の場合、点数表以外のところから出題されるところが苦手でした。『医療保険制度』『公費負担医療制度』などです。私はこの段階で医事関連法の完全知識
![]() と公費負担医療の実際知識
と公費負担医療の実際知識
![]() を購入しました。インデックスラベルを貼り、だいたいどこあたりにどんなことがらが書いてあるかも頭に入れました。最後まで胸を張って得意と言えるまでにはなりませんでしたが、なんとか正解できるようにはなりました。
を購入しました。インデックスラベルを貼り、だいたいどこあたりにどんなことがらが書いてあるかも頭に入れました。最後まで胸を張って得意と言えるまでにはなりませんでしたが、なんとか正解できるようにはなりました。
苦手分野は人それぞれ違います。それぞれの状況に応じて克服できる方法を探してみてください。通信講座を利用している方は、講師の方に質問してみてもいいでしょう。
 正答率を上げる
正答率を上げる
問題の難易度を肌で感じ、問題の癖を覚え、自分の弱点を知ったら、次は正答率を上げる努力をしてください。
早く解けることも大切ですが、それが間違っていれば合格にはつながりません。まずは正確に答えを導き出せること、それがあってのスピードです。本試験に関しても、スピードを意識して急いで解いて、見直しをする時間を確保するよりも、時間を有効に使い1回で正しい答えを導き出すことの方が合格により近いです。弱点を克服できるまで、繰り返し問題集を解いていってください。